今年度の数学部会の見学研修会は,平成23年8月9日(火)に東京情報大学において実施され,県内の各高校から40名の先生方が参加されました。その内容の概略を報告します。
1 はじめに
今回の見学研修会では,東京情報大学総合情報学部,及びカシオ計算機株式会社のご協力により,参加者は午前の部,午後の部それぞれにおいて,大学の先生方等による講義・コンピュータ実習・施設見学のいずれかから,1講座または2講座を受講しました。
2 講座
参加者は,事前の参加希望調査に基づき,午前の部として「セッション1A」と「セッション1B-1&セッション1B-2」から1つ,午後の部として「セッション2A」と「セッション2B-1&セッション2B-2」から1つをそれぞれ受講しました。
午前の部
(1) セッション1A(120分)「ビジュアルプログラミングによるサウンド処理」
講師: 東京情報大学情報文化学科長 教授 小泉 宣夫 先生
Pure Data(Pd)は,音の分析や合成をデータフローで記述していくビジュアルプログラミング言語である。画面上に部品をならべ,それらを線でつないでいくことにより,信号やデータの流れ(フロー)をつくることができるので,初心者でも親しみやすく論理的な記述に取り組めるものでした。今回の講義では,実際にプログラムに触れながら,その特徴を実感することができました。

(2)セッション1B-1(55分)「数式処理システム(CAS)による微分方程式のコンピュータシミュレーション」
講師: 東京情報大学情報ビジネス学科長 教授 三宅 修平 先生
理学・工学分野のみならず様々な分野で応用される微分方程式について,CASを使ったシミュレーション事例について解説していただきました。弾性梁の興味深い非線形現象については,2階の常微分方程式として定式化される基本式を積分操作することにより積分方程式に変換し,得られた積分方程式を離散化することにより数値シミュレーションを行い,その数値結果をCASにより可視化できることをわかりやすく示していただきました。
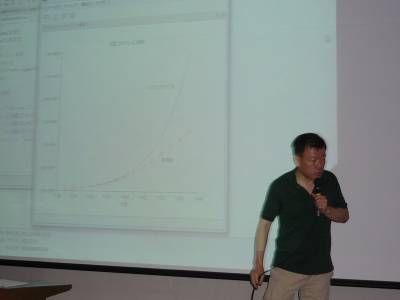
(3)セッション1B-2(60分)「授業で役立つグラフ関数電卓の活用方法」
講師: 東京都教職員研修センター 授業力向上課 教授 佐藤 公作 先生
新たに導入される『データの分析』,従来の関数領域,及び日常事象の数理的考察の領域において,数学的活動の視点から,高機能・簡単操作に進歩したグラフ関数電卓の高校数学への活用の提案をしていだきました。実際に,カシオのグラフ関数電卓の操作を体験し,知的道具としての特徴やよさを実感することができました。

午後の部
(4)セッション2A(120分)「グラフィックスプログラミング(画像処理)」
講師: 東京情報大学情報文化学科 教授 井関 文一 先生
画像に関する数学的な処理について,演習形式で講義を行っていただきました。言語に依存する部分や複雑な操作は出来るだけ表に出てこないように配慮していただきながら,画像の微分によるエッジ抽出や,単純な原理(数式)を使って非常に複雑な図形であるフラクタル図形の描画などを行いました。

(5)セッション2B-1(55分)「大学施設見学」
講師: 東京情報大学 教授 浅沼 市男 先生 他
① 8号館(東アジア環境研究の紹介)
2000年度文部科学省の研究助成を受けて「学術フロンティア・プロジェクト」を進めているとのことでした。その中核となるのが,MODISデータの恒常的受信とアーカイブです。MODISデータによって,東アジアで起きている様々な自然現象が明瞭な画像として提供されるようになったことや,米国航空宇宙局(NASA)との関わり,アンテナ受信基地における苦労など興味深い話を伺うことができました。
② 4号館(映像演習室の紹介)
映像音響分野においては,テレビ局と同じ機材やシステムを使った本格的なスタジオが完備され,研究室の活動全体が千葉市芸術文化新人賞奨励賞を受賞されました。また,学生の作品が千葉県メディアコンクールで4年連続最優秀賞に輝いているとのことでした。

(6)セッション2B-2(60分)「ネットワーク構造を利用したウイルス・ワーム防衛戦略」
講師: 東京情報大学情報システム学科 准教授 森口 一郎 先生
既存ウイルス対策ソフトではウイルスを根絶できないことと,ネットワーク構造を利用した対策手法を紹介,その有効性を解説していただきました。インターネットのつながりは「べき乗則」に従っており,従来のランダム免疫手法ではウイルスを抑制できるが根絶はできず,知人免疫手法が有効であり,これはコンピュータウイルスだけではなく現実社会(エイズワクチン接種など)へも応用可能ということでした。
