平成25年度千葉県高等学校教育研究会数学部会総会・春季研究大会が,以下の開催要項にしたがって,実施されました。
(参加人数:88名)
1 主催 千葉県高等学校教育研究会数学部会

2 後援 千葉県教育委員会
3 期日 平成25年6月14日(金)
4 会場 千葉県立市川工業高等学校
5 日程
| | 受付(弁当注文) | 09:00~ 9:40 |
| | 公開授業(2限) | 09:45~10:35 |
| | 総会 | 10:45~11:40 |
| | 連絡事項 | 11:40~11:50 |
| | 昼食 休憩 | 11:50~12:50 |
| | 研究発表 | 12:50~13:50 |
| | 講演 | 14:00~15:30 |
| | 研究協議 | 15:30~16:00 |
| | 閉会 | 16:00 |

6 内 容
(1)総会
a 挨拶(部会長,教育委員会,会場校校長,会場校数学科主任) b 議長選出 c 議事 ア 平成24年度事業報告 イ 平成24年度収支決算報告,監査報告 ウ 平成25年度事業計画案審議 エ 平成25年度予算案審議 オ 平成25年度地区委員選出及び部会長,会計監査の推薦・承認 カ その他の役員委嘱 キ その他 |
(2)研究発表
a 「平成25年度大学入試センター試験(数学)のアンケート調査結果について」 千葉県立成東高等学校 大木 喜信 先生 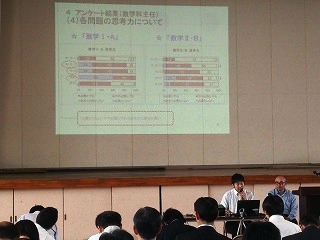 千葉県立東葛飾高等学校 加藤 純一 先生 発表内容 ア アンケート結果(受験生) ・数学の受験型,志望学部,得点分布 ・得意とする項目,苦手とする項目 ・問題ごとの難易度,正答率 ・全体を通して問題の程度,解答時間 ・受験勉強の開始時期,ⅢCの履修状況 ・数ⅠA,ⅡBの得点が共に80点以上の受験生の結果 等 イ アンケート結果(数学科主任) ・各問題の難易度,計算量,思考力等 ・問題の量,出題領域のバランス ・選択問題による難易差 等 |
b「学習意欲を高めるための工夫-学習習慣の確立を通して-」 千葉県立市川東高等学校 吉田 美佳子 先生 発表内容 学習習慣の確立を通して学習意欲の向上を目指し,自分の指導がどのように生徒たちに効果があるのか実践してみようと思った。 研究実践の方針は,まず,生徒たちが授業の内容を理解し,基礎的・基本的な知識・技能を習得し,数学を楽しいと感じることを目指すことである。次に,生徒たちが楽しいと感じた上で,数学に主体的に取り組み,家庭での学習時間を増やすことを目標とする。具体的には,計算力をつけさせ,家庭学習の時間を増やすために計画的に課題を出し,家庭学習の成果を確認するための確認テストを行い,その繰り返しの指導の中で生徒の学習意欲の向上を目指すことにする。 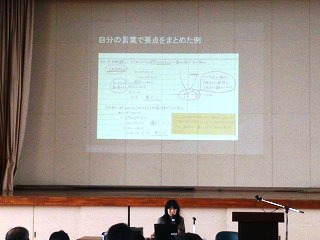 ・本校の概況と家庭学習計画,記録表の取組 ・研究実施前の生徒の把握 ・実践1-宿題プリントの取組1- ・実践2-宿題プリントの取組2- ・実践3-確認テストの取組- ・実践4-ノートの重要性を意識して学習意欲の向上をはかる- ・実践5-チェックシートの利用- ・実践6-授業のノートでの生徒の活動- |
(3)講演「日本の生徒の数学学習をどう問い直すか-学力診断,学習観,学習方略,授業設計の視点から-」
東京大学大学院教育研究科・教育学部 研究科長・学部長 市川 伸一 先生
講演の概要
(講演前の市川先生のことばより)
私たちの研究室では,この20年あまり,個別学習相談の実践研究を通じて,教科学習(とりわけ算数・数学が多い)における子どもの理解状態や学習の仕方について検討を行ってきた。「日本の子どもたちは,基礎的な学力はあるが,活用力が弱い」と言われているが,見落とされている学力,さらには学習観や学習方略の問題を強く感じる。最近行っている,学習法講座や「教えて考えさせる授業」の実践研究を通じて,数学の学力向上の方向を考えていきたい。
・自己紹介:認知カウンセリングの経験から
・認知カウンセリングから生まれた教育研究

・COMPASSにおける数学的問題解決とコンポーネント
・工夫計算
・フォローアップ講座:COMPASSの基礎力を伸ばす
・用語理解:講座の概要
・自分の学習方法を見直す
・学習観:どんな学習方法がいいと思うか
・認知心理学から見た教科の学習
・理解を重視した学習法の例
・「教えて考えさせる授業」の提案
・認知心理学から見た「理解の深まり」
・授業例:平行四辺形の面積の公式の理解
・授業例:相加平均と相乗平均の理解
・授業例:チェバの定理の理解
・「教えて考えさせる授業」は何をめざすのか
・「教えて考えさせる授業」の導入校の変化
・「教えて考えさせる授業」をめぐる最近の出来事
・「教えて考えさせる授業」関連図書の刊行
市川 伸一 先生のプロフィール
1953年(昭和28年),東京都生まれ。1977年(昭和52年),東京大学文学部卒業。1980年(昭和55年),東京大学大学院教育学研究科博士課程中退。1988年(昭和63年),「視覚的パターンの認知に関する2要因仮説とその展開」で東大文学博士。埼玉大学助教授,東京工業大学助教授。1994年(平成6年),東大助教授。1999年(平成11年),教育学研究科・教育学部教授。
かつては,認知心理学の基礎的な分野で,視覚的イメージの研究や,確率判断のバイアスの研究を行っていた。その後,教育実践との接点を求めて,「認知カウンセリング」という個別学習相談の実践を提唱し,認知心理学の考え方を学校教育や勉強法に取り入れている。最近は,地域教育の活性化をめざして,地域の学び推進機構を創立し,「学びのポイントラリー」の運営に関わっている。(以上 Wikipediaより引用)
主著に「学ぶ意欲の心理学」(2001 PHP新書),「『教えて考えさせる授業』を創る-基礎基本の定着・深化・活用を促す『習得型』授業設計-」(2008 図書文化),「勉強法が変わる本-心理学からのアドバイス-」(2000 岩波ジュニア新書)