平成27年度千葉県高等学校教育研究会数学部会総会・春季研究大会が,以下の開催要項にしたがって実施されました。
(参加人数:96名)
1 主催 千葉県高等学校教育研究会数学部会
2 後援 千葉県教育委員会
3 期日 平成27年6月19日(金)
4 会場 千葉県立佐倉高等学校
5 日程
09:00~09:40 受付(弁当注文)
09:40~10:30 公開授業(2限)
10:45~11:40 総会
11:40~11:50 連絡事項
11:50~12:50 昼食 休憩
12:50~13:50 研究発表
14:00~15:30 講演
15:30~16:00 研究協議
16:00 閉会


6 内容

(1)総会
① 挨拶(部会長,教育委員会,会場校校長,会場校数学科主任)
② 議長選出
③ 議事
ア 平成26年度事業報告
イ 平成26年度収支決算報告,監査報告
ウ 平成27年度事業計画案審議
エ 平成27年度予算案審議
オ 平成27年度地区委員選出及び部会長,会計監査の推薦・承認
カ その他の役員委嘱
キ その他
(提案されたすべての議案は,原案のとおり承認されました。)
(2)研究発表
①「平成27年度大学入試センター試験(数学)のアンケート調査結果について」

千葉県立沼南高等学校 加藤 純一 先生
千葉県立柏の葉高等学校 安田 学 先生
発表内容
ア アンケート結果(受験生)
・数学の受験型,センターの利用目的,模試の受験回数
・得意とする項目,苦手とする項目
・問題ごとの難易度,正答率
・全体を通して問題の程度,解答時間
・新課程内容の対策 等
イ アンケート結果(数学科主任)
・問題の難易度,計算量,授業充足度
・問題の量,出題領域のバランス
・選択問題による難易差 等
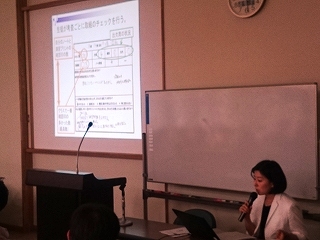
②「学習意欲向上を促す取組-ノート指導から家庭学習へ-」
千葉県立佐倉南高等学校 森川 希美 先生
発表内容
・生徒の学習とノートの様子
・主題の設定
・研究実践1 ノート指導の徹底と問題演習の取組
・研究実践2-① ノートの工夫
・研究実践2-② グループ学習の実施
・研究実践3 小テストの実施
・生徒の変化と効果
・研究実践の結果
(3)講演
「越境する数学-ユークリッド互除法と連分数-」
立教大学教授 杉山 健一 先生
講演の概要
(講演前の杉山先生のことばより)セキュリティにおいて重要な暗号理論は,自然数の素因数分解が困難であるという事実と,高校で学習するユークリッドの互除法に基づいて構築されている。そこで用いられるユークリッドの互除法は,自然数どうしの演算であるが,連分数展開に形を変えて実数の範囲にまで拡張される。連分数展開の応用範囲は極めて広く,暦の決定や音階など多方面に応用される。この講演では,連分数展開を紹介し,その興味深い応用例を解説する予定である。
講演内容
・Fibonacci数列
・我々はなぜだまされるのか?
・Cassini-Simsonの定理
・黄金比とFibonacci数列
・連分数とは
・黄金数の連分数展開
・互除法と連分数展開
・連分数の精度
・連分数展開の基本定理 など