平成27年度千葉県高等学校教育研究会数学部会秋季研究大会が,以下の開催要項にしたがって実施されました。(参加人数:104名)
1 主催 千葉県高等学校教育研究会数学部会
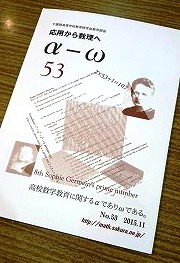
2 後援 千葉県教育委員会
3 期日 平成27年11月27日(金)
4 会場 千葉県立柏井高等学校
5 日程
| | 受付(弁当注文) | 9:00~ 9:40 |
| | 公開授業(2限) | 9:45~10:35 |
| | 開会・挨拶・諸連絡 | 10:45~11:05 |
| | 研究発表① | 11:10~11:40 |
| | 研究発表② | 11:40~12:10 |
| | 昼食・休憩 | 12:10~13:10 |
| | 研究発表③ | 13:10~13:40 |
| | 研究発表④ | 13:40~14:10 |
| | 講演 | 14:20~15:50 |
| | 研究協議 | 16:00~16:20 |
| | 閉会 | 16:20 |
6 内容
(1)研究発表
①「平成27年度計算力テスト実施結果について」

(千葉県立大原高等学校 三浦徳幸先生)
- 研究の目的
- 出題方針
- 実施状況
- グループ別の得点
- 設問別正答率の比較
- 個人の得点による比較
- 正答率の比較
- 意見・感想等
- おわりに
②「平成27年度大学の入試問題に関する研究」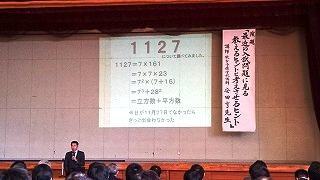
(千葉県立成田北高等学校 和田匡史先生)
- はじめに
- 研究の内容
- 研究対象の大学について
- 日本大学理工学部の概要
- 平成27年度の入試方式について
- 問題に関する研究委員会の分析方法について
- 問題の実際と研究委員の分析
- 大学側との意見交換について
- 終わりに
③「キャリア教育の視点に立った教科指導に関する研究

-数学的活動とキャリア教育との結びつきについて-」
(千葉県立浦安南高等学校 奥田雅之先生)
- 話の前に・・・・・・
- キャリア教育について
- 数学的活動との結びつきについて
- 実践紹介
実社会で必要とされる基礎計算力の向上に関わる数学的活動
パズル等を活用した思考力や発想力の向上を目指す数学的活動
他教科との関連性を考慮した実社会に即した数学的活動 - 最後に・・・・・・
- おまけの話1
- おまけの話2
④「教育課程アンケートについて」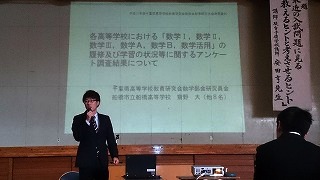
(船橋市立船橋高等学校 齋野大先生)
- はじめに
- 今回の学習指導要領による主な変更点
- 調査について
- 調査の集計結果および考察,今後の課題等
- 数学Ⅲ・の履修状況
- 数学Ⅲの単位数の適切度
- 数学Ⅲの履修順序
- 数学Ⅲの指導内容
- 言語活動の充実について
- 次の学習指導要領改訂に望むこと
- 新テストについて
- おわりに
(2)講演
演題「最近の入試問題に見る教えるヒントと考えさせるヒント」
講師 駿台予備学校講師 安田亨先生
1 不等式の問題
- 三角不等式の有用性
- 文字の多い問題に慣れることが必要(H15東京医歯大・医)
- 生徒のレベルに合わせた教材に不満を感じる生徒もいる
- 複素数は幾何よりも代数や解析への応用が重要(H15山形大・医)
2 間違いやすい問題
- 格子点を通る道順の問題(H15東北薬科大・前期)
- 文字係数を含む連立2次不等式の問題(H15奈良教育大)
- 文字定数を含む不等式の領域を図示するときは,場合分けをしない
(正領域,負領域の考え方) - 文字が多いときは視覚化をする
3 図形の良問
- 三角形の辺や角に関する問題(H15福岡教育大・後期)
- 図形問題のアプローチ・・・図形的,三角関数,ベクトル,座標計算
- 図形は意識的に着目する場所を替える
- 三角形,四角形の面積が最大となる問題(H15愛媛大・医)
- 宇宙の調和に反している(面積が最大になるときの対称性)
- 困難は分割せよ(多変数の扱い)
4 基本を問う
- 連立指数方程式の解の存在(H15東北大・理AO)
- 方程式の解の存在の有無
終わりに- 積分方程式(H15東京海洋大・海洋工)
- 過去に出ていた問題が出ることがある
- 2015年で一番感心した問題‐確率の問題(H15宮崎大・前期)
- 出題者に負けないように,出題者が喜んでくれる解答を